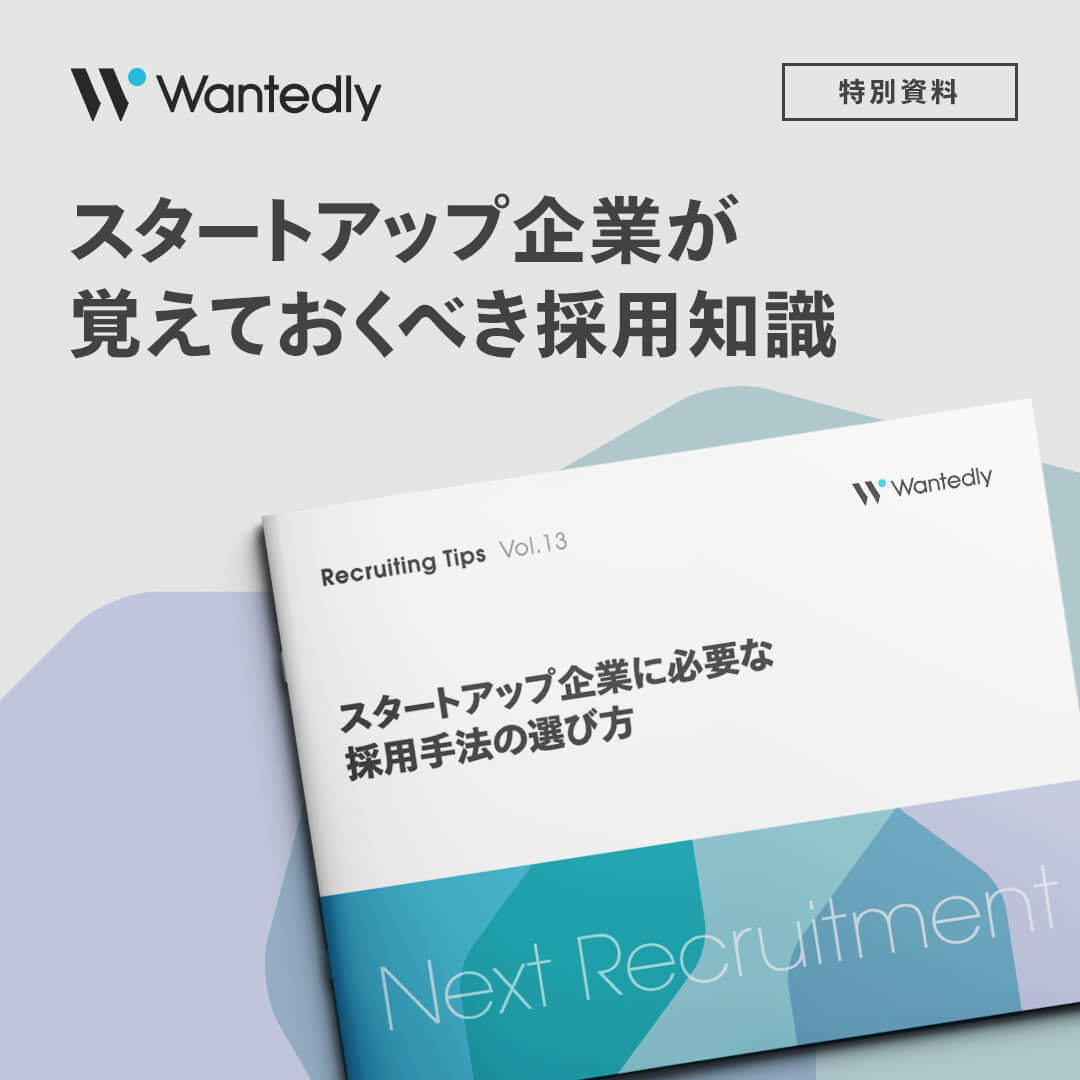採用ブランディングが企業にとっての課題として注目されています。人手不足の顕在化で転職潜在層への訴求が必要との認識が広がっており、採用ブランディング戦略に基づく採用広報が施策として重要になっているためです。
しかし、採用マーケティング、採用ブランディング、採用広報の概念や考え方の違いを正しく説明できる採用担当者はまだ多いとは言えません。そこで前回、「採用マーケティング」「採用ブランディング」「採用広報」の違いと役割について解説しましたので、今回は採用ブランディングを掘り下げます。
採用広報を始めたいけど、何から始めれば良いかわからない方へ
Wantedlyなら、誰でも簡単に会社のページや採用ブログを作成することができます。
作成したページはGoogleの検索結果の1ページ目に表示されやすく、オウンドメディアとしても活用できます。
まずは手軽に採用広報を開始したい方、ぜひ資料をダウンロードして詳細を確認してみてください。
とくに採用ブランディング戦略を策定するために役立つ考え方を網羅していますので、ぜひご覧ください。
▼採用マーケティング、採用ブランディング、採用広報の違いと役割を解説
採用ブランディングとは
採用ブランディングの概念や採用広報との違い、また採用ブランディングの導入がもたらすメリットを説明します。
1.採用ブランディングとは
採用ブランディングは求職者の自社に対する興味・関心を集め、応募・入社意欲を高めてもらうための戦略です。自社の「ブランド化」を目的とする取り組みであることから「採用ブランディング」と呼ばれています。
採用競合となる他社と比較した場合の優位点や自社が持つ固有の特長を発信し、「働く場所」として魅力的であると訴求する施策です。
採用ブランディングは新卒・中途を問わず採用活動における大きな課題となっています。2024年12月に株式会社コーナーが企業の人事部門を対象に実施した調査では、新卒採用・中途採用ともに「採用ブランディングの強化」が最大の課題となっています。
「新卒採用はチャネルの最適化やブランディングの基盤構築が課題」
「中途採用の方がより課題感が強く、(中略)複数のオファーを比較する候補者の傾向から、よりブランディングの構築が鍵になっている」
採用ブランディングを通じて、求職者や転職潜在層に「働く場所」として魅力的だと感じてもらえれば、採用活動を有利に進められます。
しかし、自社を客観視して競合他社と差別化し、「働く場所」として魅力的であると訴求するのは容易ではありません。そこで今回は、採用ブランディング戦略の構築に役立つ6つの考え方を紹介します。
引用:【株式会社コーナー】【2025年採用戦略】企業規模別の施策トレンドと成功事例を公開
2.採用広報との違い
採用ブランディング戦略に役立つ考え方を解説する前に、採用ブランディングと採用広報の違いを整理しておきましょう。自社をブランド化し、魅力ある企業として認知してもらうためには、「誰に」「何を」「どこで」に分けて考える必要があります。
採用ターゲットに含まれない母集団が形成されても、採用活動が成功したとは言えません。どんなスキルやカルチャー、考え方を持つ人材をターゲットとするのか、つまり「誰に」を定義します。
そして、次に考えるべきなのが「何を」訴求するのかであり、採用ブランディングにおいて核となる部分です。「働く場所」として魅力を感じてもらえる要素を再整理し、求職者や転職潜在層の興味・関心を引き出します。
一方、採用広報は具体的な情報発信施策です。情報発信にあたっては、会社説明会や求人メディア、採用動画などさまざまなチャネルの中から、「どこで」伝えるのかを検討します。
自社が求めている人材にリーチしないプラットフォームで展開しても、十分な効果は期待できないからです。ターゲットとなる「誰に」、採用ブランディング戦略に基づく「何を」、そして採用広報における「どこで」の3つの最適化によって、採用活動の成功がもたらされます。
3.採用ブランディングのメリット
採用ブランディングのメリットについても確認しておきましょう。採用ブランディング戦略を練るにあたっては、何を目的に自社の魅力を整理するのか、最終的にどのような採用ブランドとして意識してもらいたいのか、を念頭に置きながら考える必要があるためです。
採用ブランディングのメリットは5つあげられます。
1.認知度を高め理解を深められる
採用ブランディング戦略に基づく情報発信を通じてリーチを増やし認知度を高めます。また、求職者はもちろん、転職潜在層に対しても自社への理解を深められます。
2.ミスマッチを防止できる
採用ブランディングによってカルチャーマッチ、ミッションマッチする人材からの応募増が期待できます。自社とマッチしない人材からの応募抑制につながる「セルフ・スクリーニング」効果から、ミスマッチの防止にもつながります。
3.競合他社と差別化できる
採用ブランディングは「自社ならでは」の魅力を発信するための戦略であるため、採用活動で競合する他社との差別化が可能となります。「この会社で働きたい」と思ってもらえる状況を作り出すのが、採用ブランディングです。
4.採用コストを削減できる
採用ブランディングを通じて自社への認知が広まり理解が深まると、マッチする人材からの応募が集まるようになります。そのため、求人メディアを通じた募集や人材紹介サービスを利用した採用活動より、採用コストを削減できます。
5.従業員エンゲージメントが向上する
インナーブランディングにも効果を発揮します。いままで整理できていなかった自社の魅力を社員が再認識できるためです。
業務へのモチベーションが向上し、自社に対するエンゲージメントが高まるため、業績への貢献も期待できます。
採用ブランディングに役立つ考え方6選
採用ブランディング戦略を構築するには、自社の魅力を正確に言語化する必要があります。ここでは、採用ブランディングを進めていくうえで役立つ考え方を6つ紹介します。
1.EVP(Employee Value Proposition)
EVPは「Employee Value Proposition」の略で、「従業員価値提供」を意味します。企業が従業員に対して提供できる価値を指しています。
企業が従業員に提供できる価値としてわかりやすいのは給与やボーナスなどの報酬がありますが、EVPは他の要素も含む概念です。オフィス環境(カルチャー、チームワークなど)、キャリア機会(昇進、スキルアップなど)、社会的価値(ミッション、ビジョンなど)も該当します。
企業の取組みとしてEVPが注目を集めるのは、人材の流動化や価値観の多様化が影響しているためです。終身雇用制度が崩壊し中途採用の比率が高まるにつれて、企業は優秀な人材を獲得するために、従業員に対して提供できる価値に向き合うようになってきました。
また、人々の価値観が多様化し、企業に対して求める要素が多岐にわたるようになっています。給与・ボーナスなど報酬を重視する人材もいれば、ワークライフバランスの充実を優先したいと考える人材、仕事を通じて社会貢献したいと考える人材も少なくありません。
採用ブランディング戦略を構築するにあたって自社の魅力を見つめ直す上でもEVPの定義は効果的です。採用ブランディングの導入にあたっては、自社が従業員に対してどんな価値を提供できるのかを、EVPを通じて明確にしておくと良いでしょう。
2.Candidate Persona(求職者ペルソナ)
採用ブランディングを展開するうえでは、自社の魅力として「何を」伝えるのかを分析するとともに、「誰に」にあたるターゲットの選定も重要な成功要素です。
自社にマッチしない人材層にリーチしても反応が乏しい上に、入社してもミスマッチから早期離職につながってしまう可能性が高いでしょう。どのような人材層をターゲットとするのかを決める上で用いられるのがCandidate Persona(求職者ペルソナ)です。
ペルソナはマーケティング業界で一般的に利用されている概念で、商品やサービスの購入層を分析するために用いられます。マーケティングにおけるペルソナを採用活動に利用するのが「Candidate Persona」で、自社にとって理想的な求職者のプロファイルを作成し、役立てます。
Candidate Personaは採用ターゲットと混同されるケースも少なくありませんが、詳細に定義し架空の人物像を作り上げるのが特徴です。年齢や性別、スキル・経験だけでなく、キャリア目標から価値観、情報収集手段に行動パターンまで、自社が採用したい人物像を具体的に作り上げます。
Candidate Personaを明確にすると、自社とのマッチ度が高い人材に対して効率的で適切なアプローチが可能になるためです。また、採用担当者と経営陣や現場で認識のズレを防止する効果も期待できます。
採用ブランディングにおいて「何を」自社の魅力として伝えるのかと同時に、「誰に」対して情報発信するのかを、Candidate Personaで定めておきましょう。
3.インバウンドリクルーティング
人手不足が続き採用競争が激しくなる中で注目を集めているのがインバウンドリクルーティングです。マーケティングの世界では見込み客と中長期的な関係を構築し、自社の商品・サービスに興味を持ってもらう手法がインバウンドマーケティングとして定着しています。
この手法を採用活動に取り入れたのがインバウンドリクルーティングです。インバウンドリクルーティングはすでに転職活動を行っている転職顕在層だけでなく、まだ転職を検討していない転職潜在層までターゲットにするのが特徴です。
オウンドメディアやプレスリリース、動画などさまざまなコンテンツを通じて情報を発信し、転職意欲の有無にかかわらず自社に関心を持ってもらい、長期的な関係を構築します。自社への興味が高ければ、人材が転職を検討する際に転職先として想起してもらえるからです。
近年、採用活動におけるアウトバウンドリクルーティングに注目が集まっていました。企業側から候補者にアプローチして、応募を促す採用手法です。
しかし、すでに転職を考えている優秀な人材に対しては多くの企業がスカウトを送っているため競争率が高い一方、まだ転職を考えていない人材にコンタクトしても、興味を持ってもらえる可能性は多くありません。
インバウンドリクルーティングなら、人材との長期的な関係の構築によって効率よく母集団を形成できます。インバウンドリクルーティングは採用ブランディングを展開する上でベースとなる考え方であり、タレントプールの重要性への認知が広まるとともに、採用活動全体においても重要性が高まっています。
4.ゴールデンサークル
採用ブランディングでは、説得力のある伝え方も意識しておく必要があります。そこで役立つのが「ゴールデンサークル理論」です。
ゴールデンサークル理論はマーケティングコンサルタントのサイモン・シネックが過去の優れたプレゼンテーションから導き出し提唱した、人の心を掴むための方法論です。
従来、プレゼンテーションは「WHAT(何を)」「HOW(どうやって)」の順番で行われるのが一般的でした。しかし、ゴールデンサークル理論ではまず「WHY(なぜ)」を説き、それから「HOW(どうやって)」「WHAT(何を)」の順番で伝えるのが効果的、とされています。
企業の商品プレゼンテーションを例としてあげてみましょう。「WHAT(何を)」にあたる商品の解説から話をはじめると、人々の関心はスペックや機能に集まってしまいます。
しかし、「WHY(なぜ)」にあたる商品開発の背景から語ると、どんな課題を解決するために開発したのか、どんなメリットを享受できるのかなど、人々の感情を揺さぶり共感を引き起こすストーリーを構築できます。
ゴールデンサークル理論はマーケティングの世界で大きな反響を呼び、先進的な企業を中心に広まりました。そして、ゴールデンサークル理論は採用ブランディングにおいても効果を発揮します。
「WHY(なぜ)」で企業のミッション・ビジョン・バリューなど会社の存在意義や社会的な価値を語り、「HOW(どうやって)」で他社と異なる強みや価値の提供方法を解説します。さらに「WHAT(何を)」で具体的な業務を説明すると、候補者は企業に好感を持ちやすくなるためです。
ゴールデンサークル理論はWantedlyの募集ページにも導入されています。企業のアウトラインを「なにをやっているのか」で示した後、「なぜやるのか」「どうやっているのか」「こんなことやります」と、「WHY(なぜ)」「HOW(どうやって)」「WHAT(何を)」の順番で語るよう設計されています。
採用ブランディングを展開する上では、訴求すべき自社の魅力をどのように伝えるか考えるうえで、ゴールデンサークル理論を活用しましょう。
5.6Cフレームワーク
採用ブランディング戦略を策定する上で、採用マーケティングの観点から最適化を図るフレームワークが「6Cフレームワーク」です。
採用マーケティングは採用活動にマーケティングの手法を取り入れる考え方で、近年多くの企業が取り組みを強化しています。マーケティングにおいて消費者が商品・サービスを購入するまでのプロセスを採用活動に当てはめ、内定・入社までの段階を以下のようにファネルとして定義し改善を図るのが特徴です。
Awareness(認知)
Interest(興味)
Consideration(検討)
Application(応募)
Selection(選考)
Hire(採用)
6Cフレームワークは各ファネルを最適化するために用いられ、次の6つの要素から構成されます。
Contents(コンテンツ):求人情報や企業文化を伝えるための具体的な素材。
Channels(チャネル):SNSや採用イベント、オウンドメディアなどの情報発信経路。
Community(コミュニティ):自社のファンやタレントプール、社員ネットワークなど双方向の交流手段。
Candidates(候補者):求める人材像、ペルソナによる企業にとっての採用ターゲット。
Conversion(コンバージョン):応募や面接に誘導するための導線。
Culture(文化):ミッション、ビジョン、バリューやカルチャー、価値観。
採用ブランディングにおける6Cフレームワークの活用は、Awareness(認知)からHire(採用)に至る各ファネルごとに6要素の最適化を念頭に置いて行います。各ファネルごとにどのような採用ブランディングを形成すべきかを考える施策であるため、採用ブランディング戦略の高度化につながります。
6.パーパスドリブン
企業がブランディング戦略を考える上で、パーパスドリブンの重要性が高まっています。パーパスドリブンとはPurpose(パーパス・目的)をDriven(主導)するキーワードで、企業が追求すべき社会的な価値であるパーパスに基づいて事業運営を展開する考え方です。
パーパスを企業経営における指針として機能させると、事業展開の方向性が明確になり社員の働きがいや満足度が高まります。また、消費者からの信頼を獲得できるため、ブランド価値を向上させることが可能となります。
採用ブランディングにおいてパーパスドリブンの考え方が重要度を増しているのは、求職者が企業の社会的価値を重視するようになっているためです。
従来、求職者は給与など報酬、それに休日休暇といった福利厚生を中心に企業を選んでいました。しかし、価値観の多様化が進行し企業がどのような社会的価値を提供しているのか、目指しているのかといった点に着目するようになっています。
パーパスドリブンに基づいた採用ブランディングでは、企業の使命であるパーパスと、求職者の価値観が一致した状態がゴールです。そのためには、企業が提供できる社会的インパクトやビジョンを明確に示し、求職者の共感を呼ぶメッセージを発信する必要があります。
採用ブランディング戦略を構築する中で、自社の魅力を整理し定義するにあたってパーパスドリブンを意識したメッセージングは、今後必要不可欠となっていくでしょう。
採用ブランディングにWantedlyが最適な理由
採用ブランディング戦略に基づく情報発信には、Wantedlyが最適な理由を3つの点から説明します。
1.企業の魅力を自由に発信できる
Wantedlyなら、採用ブランディング戦略で定めた自社の魅力を効果的に発信できます。企業の魅力はさまざまな要素から構成されており、最適な発信方法は企業ごとに異なります。
文章で訴求するのがベストな場合もあれば、ビジュアルに訴えるのが効果的なケースもあるでしょう。Wantedlyのストーリーなら、コンテンツを自由な形式で発信できます。
トップに表示されるカバー画像は縦1,120px、横2,560pxで、パソコンなら迫力あるサイズで自社ならではの特徴を伝えられます。一方、本文内に表示される画像のサイズは自由であり、企業ごとに最適な大きさで魅力を訴求可能です。
もちろん、外部サイトの埋め込みもできるので、すでに展開しているさまざまなコンテンツとの連動も自在であり、使い勝手の良さが特長になっています。Wantedlyなら自社のカルチャーや各種制度の説明、個性的な社員の紹介など、あらゆるコンテンツの発信に最適です。
2.企業の価値観を訴求できる
価値観が多様化し、求職者はさまざまな軸で会社を選ぶようになっています。ワークライフバランスの充実を求める求職者もいれば、社会貢献を重視して会社を探す求職者もいるなど、企業の個性が問われる時代になっています。
Wantedlyは自社の価値観を効果的に訴求できるのが特長です。トップページでは40以上の選択肢の中から重視する価値観を選べるようになっており、求職者は共感できる企業を探しやすくなっています。
選択した価値観はそれぞれに説明を追加できるようになっているため、深い理解を促せます。また、募集ページは「なにをやっているのか」「なぜやるのか」「どうやっているのか」など、企業の「なぜ」を切り口にした構成です。
ゴールデンサークル理論に基づき、求職者の理解を促進し共感を醸成しやすい形で説明できるよう配慮しているためです。Wantedlyなら、企業は自社の価値観をわかりやすく伝え、ミッションマッチ・カルチャーマッチする求職者へのアプローチに最適です。
3.多くの求職者にリーチできる
採用ブランディングにおいても、認知の最大化は効果を高めるための重要な要素です。
ターゲットとなる人材を詳細に設定しても、求める人材層にリーチしなければ効果は高まらないからです。採用ブランディング戦略に基づく採用広報の展開においては、最適なプラットフォームの選択が鍵となります。
Wantedlyには20代・30代の若年層を多く含む400万以上の会員が登録しており、ターゲット人材へのリーチが可能です。もちろん、採用が難しいエンジニア・技術者も数多く含まれています。
また、ダイレクトスカウトを利用して優秀な人材への直接アプローチができるのも特長です。ダイレクトスカウトは自社を認知していない候補者に向けて企業が直接情報を届け、関心を持ってもらう施策のため「攻めの採用」とも呼ばれています。
優秀な人材が数多く登録しており、企業が人材に直接情報発信できるダイレクトスカウトまで可能なWantedlyは、採用ブランディングの効果を高めるための最適なプラットフォームです。
まとめ
今回は採用ブランディングに役立つ6つの考え方を紹介しました。採用ブランディングはあらゆる角度から自社の魅力を整理し、定義した上で効果的に伝える施策です。
また、採用活動における各ファネルで何をどのような手法で訴求すべきなのかについても、考える必要があります。採用ブランディングの最適化はとても難しいからこそ、さまざまな角度からの検討が求められます。
今回紹介した6つの考え方を役立てて、自社の採用ブランディングを成功させましょう。